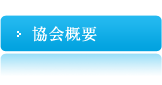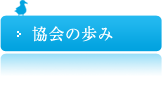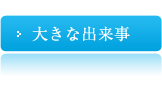神戸旅客船協会の大きな出来事
home > 現在のページ
フェリー化の進展等
協会設立当初は、四国・淡路島・家島諸島等と本土間の貨客航路、神戸港等の港に入港する外航船と陸地間の通船航路、鳴門観潮等の観光航路を行う事業者が中心であった。
その後、自動車をそのまま載せることができる自動車航送船(フェリー)が登場することとなるが、このうち昭和29年4月に開設された明石~岩屋間、福良~鳴門間の2航路が日本初の本格的なフェリー航路とされている(福良~鳴門は昭和60年まで運航、明石~岩屋は平成22年まで運航していた。)。
また、昭和40年代の日本経済の高度成長に伴うモータリゼーションの著しい進展は、フェリー航路の発展を促し、旅客航路事業の性格を大きく変えた。
昭和43年には小倉~神戸間、翌44年には大分~神戸間でフェリー航路が開設されたが、これらの航路は日本におけるいわゆる長距離フェリー(航路距離300km以上)の先駆けとされている。その後、道路混雑の慢性化や運転者労働力の不足などと相まって全国的な長距離フェリー網が出来上がっていった。
一方、昭和40年代においては、国の経済計画に対応した港湾整備5カ年計画が数次にわたり行われ、港湾の整備が格段に進展した。そのため、外航船等が接岸すべき岸壁に空きがなく港に入港できず港外で沖待ちするといった状態が激減し、沖待ちする外航船と港を結ぶ通船事業の需要は減少していった。
本四連絡橋神戸淡路鳴門ルートの全面開通
 本州四国連絡橋神戸・鳴門ルートの架橋工事は昭和51年7月大鳴門橋の起工式が行われスタートした。
本州四国連絡橋神戸・鳴門ルートの架橋工事は昭和51年7月大鳴門橋の起工式が行われスタートした。「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客船定期航路事業等に関する特別措置法」が昭和56年11月施工された。
本特別措置法は本四架橋に伴い一般旅客定期航路 事業及びその関連事業が受ける影響を軽減するため制定されたもので、その概要は、①一般旅客定期航路事業等の再編成 ②一般旅客定期航路事業を営む者に関する措置③一般旅客定期航路事業等離職者に関する措置 であった。この法律に基づき、国、本四公団、自治体が航路廃止・縮小する事業者対策及び離職者対策にあたった。
平成7年1月建設中の明石海峡大橋のやや南東よりのほぼ直下を震源とする阪神
・淡路大震災に見舞われたが、橋長が約1m伸びたもののこれらの変位は耐震設計の許容範囲内と認定され、工事は約1ヶ月中断されただけで続行された。

本州四国連絡橋神戸鳴門ルートは、平成10年4月「明石海峡大橋」の完成により、全線開通した。これに伴い関係航路の事業規模の縮小等を余儀なくされた事業者は、航路の廃止7社12航路、航路の規模縮小8社8航路。架橋供用の日以降6ヶ月間においてさらに航路の廃止4社4航路、航路の規模縮小1社1航路となり、離職を余儀なくされた従事者は1,752名を数えた。
明石海峡大橋供用開始日以降1年間に会員56社から16社が退会し、大打撃を受けました。
阪神・淡路大震災による混乱にあって旅客船・フェリーの活躍
 ①平成7年1月17日午前5時46分に発生した兵庫県南部地震は道路、鉄道、港湾施設にも甚大な被害をもたらし、過去にない大震災となった。神戸・阪神間の主要幹線交通である鉄道は多くの線区で分断され、さらに、主要道路は各地で寸断、陸上交通も困難を極めた。そのため旅客船による海上代替え輸送が行われ大いに活躍した。
①平成7年1月17日午前5時46分に発生した兵庫県南部地震は道路、鉄道、港湾施設にも甚大な被害をもたらし、過去にない大震災となった。神戸・阪神間の主要幹線交通である鉄道は多くの線区で分断され、さらに、主要道路は各地で寸断、陸上交通も困難を極めた。そのため旅客船による海上代替え輸送が行われ大いに活躍した。震災により、旅客船・フェリーの受けた直接被害は軽微であったが、神戸港の港湾施設が倒壊ま
 たは損傷を受け利用できなかった埠頭に発着していたフェリーは、その航路の起終点を大阪港に変更したのが8航路あった。岸壁等港湾施設の損壊が軽微で旅客船・フェリー等の発着に支障がなかった既存航路は利用者からの要請を受け増便を行ったのが6航路。また、運輸省(現:国土交通省)、一般利用者、神戸市等自治体からの要請により、損傷が軽微で利用が可能であったメリケン波止場東側岸壁等を利用し、新規に開設した臨時航路が神戸~大阪航路など11航路となっている。
たは損傷を受け利用できなかった埠頭に発着していたフェリーは、その航路の起終点を大阪港に変更したのが8航路あった。岸壁等港湾施設の損壊が軽微で旅客船・フェリー等の発着に支障がなかった既存航路は利用者からの要請を受け増便を行ったのが6航路。また、運輸省(現:国土交通省)、一般利用者、神戸市等自治体からの要請により、損傷が軽微で利用が可能であったメリケン波止場東側岸壁等を利用し、新規に開設した臨時航路が神戸~大阪航路など11航路となっている。これら震災後新設された臨時航路における輸送人員は、1月下旬において最大約2万人/日となり、その後鉄道の開通区間の増加に伴い2月下旬に向けて急速に減少し、全線開通したことをもって役割を終えた。なお、新設された航路は、1月20日から8月31日の間に、延べ約642千人を輸送した。(JR西日本の東海道線の全線開通は4月
 1日、阪急電鉄神戸線全線開通6月12日、阪神電鉄本船全線開通6月26日)
このように、マヒ状態に陥った陸上交通に対し、その代替えとしての海上交通は大いに活躍し、のち運輸大臣等から感謝状が授与された。(公益財団法人関西交通経済研究センター平成7年10月発行「震災等発生時の旅客交通に関する調査研究報告書」から抜粋)
1日、阪急電鉄神戸線全線開通6月12日、阪神電鉄本船全線開通6月26日)
このように、マヒ状態に陥った陸上交通に対し、その代替えとしての海上交通は大いに活躍し、のち運輸大臣等から感謝状が授与された。(公益財団法人関西交通経済研究センター平成7年10月発行「震災等発生時の旅客交通に関する調査研究報告書」から抜粋)阪神淡路大震災の概要等は国土交通省HP、兵庫県HP、神戸市HP等参照
②ホテルシップ、お風呂シップ等 地震発生以来多くの市民が学校等避難所に避難し、かつ、ガス・水道が使えない中での不自由な生活を送ることとなった。旅客船は、快適な生活空間であることから、クルーズ客船等で利用可能な客船を神戸港、津名港、尼崎港等の岸壁で係留し、ホテルシップとして利用された。
また、岸壁の乗降設備が損壊し、フェリーの発着が出来ないため就航できなかった神戸-高松航路のフェリー4社6隻が、高松で水と燃料を積載し、東神戸フェリー埠頭に係留して、船内浴室を無料開放、1月25日から2月2日までお風呂シップとして活躍した。
これらのサービスを利用した被災者は最大1日2千人に上った。